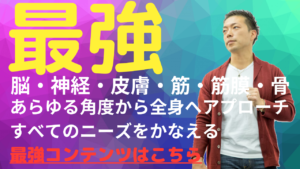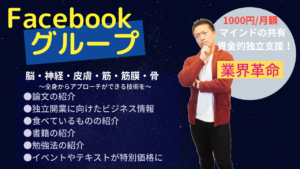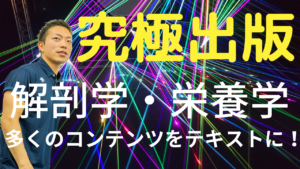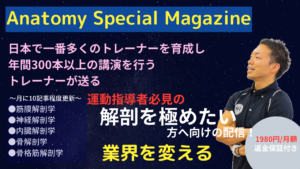1|まず「ダイエット」は“脂肪細胞の生物学”の話である
多くの人がダイエットを「カロリー計算」「運動量の増減」と捉えているが、実際にはもっと多層的で、脂肪細胞(Adipocyte)の生理を理解しなければ正しい介入はできない。
脂肪細胞は単なるエネルギーの貯蔵庫ではなく、
ホルモン分泌(レプチン、アディポネクチン)
免疫調整(炎症性サイトカイン)
神経系との相互作用(迷走神経・視床下部)
といった内分泌器官そのものである。
ゆえにダイエットを語る上では、
「脂肪細胞が“減る"のではなく、“縮む”だけである」
という生物学的前提を持つ必要がある。
2|“痩せる”は代謝の話ではなく、恒常性(Homeostasis)の話である
人が太る・痩せるは単純な数式ではなく、
視床下部を中心とした恒常性(ホメオスタシス)システム
によって強烈に守られている。
●セットポイント理論(Set-point theory)
脳が「あなたの適正体重はここ」と勝手に決めており、
そこから大きくズレると、
代謝を落とす
食欲を上げる
活動量を下げる
レプチン感受性を下げる
などの**“自動的な防御反応”**が起きる。
つまり、
痩せにくさは意志ではなく神経生理学の問題である。
3|カロリー理論は正しいが“不十分”である
「摂取<消費で痩せる」これは正しい。
だが、指導者が知っておくべきなのは、
この式が**生物学的には“最後の結果”**に過ぎないという点だ。
カロリー収支は以下の影響を受ける:
●①NEAT
姿勢維持・小さな身体活動
→肥満者では自動的に低下する(脳の防御反応)
●②腸内環境
同じ量の食事でも吸収効率が異なる
→Firmicutes比率が高いと吸収効率↑
●③甲状腺ホルモン
代謝率を数十%単位で変化させる
●④筋量・ミトコンドリア
筋の質(ミトコンドリア密度)がBMRに大きく影響
●⑤ストレス・睡眠
コルチゾール上昇 → 内臓脂肪蓄積 → 代謝低下
結論:
「痩せる=カロリー至上主義」ではなく「痩せる=システム介入」
という視点に切り替える必要がある。
4|行動科学のエビデンス:脳が“ダイエットを嫌う”理由
ヒトの脳は進化的に、
「飢餓=死」
という環境で長く生きてきた。
そのため、
痩せる=脳にとって脅威
である。
5|運動のエビデンス:筋トレは「消費」ではなく“代謝再設計”である
脂肪減少目的で
「ランニングばかりするのは効率が悪い」。
これは明確なエビデンスがある。
●筋トレの痩身効果は“後発的”である
筋量増加 → BMR上昇
ミトコンドリア密度増加 → 脂肪酸酸化↑
GLUT-4増加 → インスリン感受性改善
姿勢保持筋の活性 → NEATの自動増加
要するに筋トレは、
「痩せやすい身体システム」を作る行為である。
6|ダイエットにおける神経介入の重要性(運動指導者はここを語れ)
あなたの専門分野を活かすパート。
●①迷走神経(Vagus nerve)
食欲抑制系(副交感)の安定は、
食欲の暴走を抑える。
深呼吸・胸郭可動性・内臓のポジション改善は
迷走神経トーン改善=過食抑制につながる。
●②前頭前野(PFC)
衝動食い・夜食はPFCの疲労が背景。
→ストレス管理、運動、睡眠介入が必須。
●③脳幹・前庭系
姿勢不良 → 呼吸低下 → 自律神経の偏り → 過食につながる
つまり、
姿勢 × 呼吸 × 脳幹の介入はダイエットの前提条件
である。
7|栄養学のエビデンス:食事法は“体質×心理×生活環境”で選べ
一般的に研究で優位性が高い食事法は以下
地中海食
高タンパク食
糖質制限(短期は強い)
1800kcal前後の持続型カロリー制限
だが、最強の食事法は「続けられる食事法」である。
行動科学のメタ分析によれば、
“継続要因”が体重減少成果の70%以上を占める。
8|睡眠のエビデンス:睡眠不足は太る“独立した因子”
睡眠不足が2日続くだけで:
グレリン上昇
レプチン低下
衝動性増加(PFC機能低下)
脂肪酸代謝低下
つまり、
睡眠はカロリー計算より優先される問題である。
9|ストレスとホルモン:コルチゾールは「内臓脂肪ホルモン」
慢性的ストレス → コルチゾール↑
→ 肝臓の糖新生↑
→ インスリン↑
→ 内臓脂肪蓄積
と完全に“太るライン”が形成される。
だからこそ、
**呼吸・瞑想・姿勢改善・感覚入力(手足)**など
自律神経に介入できるトレーナーは価値が高い。
10|結論:ダイエットは“脳・身体・生活”の総合アプローチでしか成立しない
まとめると、ダイエットのエビデンスは以下の10層で成り立つ:
カロリー収支
内分泌(レプチン・甲状腺・インスリン)
脂肪細胞の生物学
ホメオスタシス(セットポイント)
食行動の神経学
腸内環境
運動(筋トレ・NEAT・ミトコンドリア)
睡眠
ストレス(コルチゾール)
姿勢・呼吸・迷走神経
つまり、
ダイエットは“脳 × 解剖学 × 生理学 × 行動変容”の複合領域である。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。