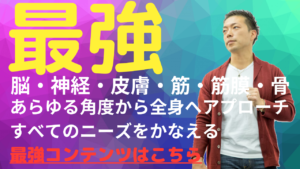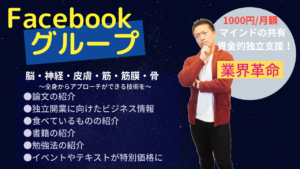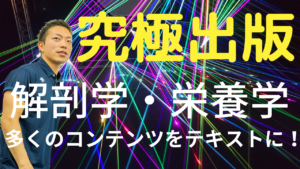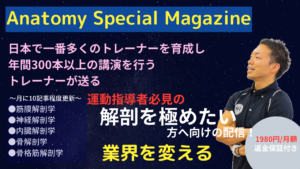| 視点 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ❶ 分子栄養学・代謝経路からの視点 | アミノ酸が体内でどのように使われ、エネルギーやホルモン、解毒、抗酸化物質に変換されるかを解説 | メチオニン → システイン → グルタチオンなど |
| ❷ 病態・不定愁訴からの視点 | アミノ酸不足や代謝異常がどのような体調不良・症状(疲労、うつ、不眠など)と関連しているか | トリプトファン不足 → セロトニン低下 → 睡眠障害 |
| ❸ 運動指導現場の臨床応用視点 | 具体的なクライアント事例(疲れやすい/筋肉痛が治りにくいなど)に対して、どのアミノ酸がどう作用するかを展開 | 筋肉痛が残りやすい → グルタミンorEAAの導入など |
| ❹ 進化・生物学的視点 | なぜ人類は必須アミノ酸を合成できなくなったのか?タンパク源の摂取行動はどう進化したか? | 植物食中心の時代/動物性タンパク獲得の進化圧力 |
| ❺ アミノ酸の神経学的作用視点 | 情動・意欲・集中力・感情コントロールにおけるアミノ酸の役割を解説 | チロシンやトリプトファン → ドーパミン・セロトニン系に影響 |
はじめに:なぜ「アミノ酸=筋肉」の常識は一面的か?
アミノ酸は神経系の調整役でもある
脳とアミノ酸:思考・感情・覚醒を左右する化学物質
トリプトファン → セロトニン → 睡眠・安心感
チロシン → ドーパミン/ノルアドレナリン → やる気・集中
「疲れが抜けない人」に共通する栄養学的背景
カフェイン依存とチロシン不足
セロトニン→メラトニンへの変換低下で睡眠の質が落ちる
ストレスとアミノ酸の消耗
ストレス時にグルタミン・BCAAが枯渇するメカニズム
筋肉だけでなく「脳疲労」にも影響
食事で補うべきアミノ酸とそのタイミング
朝:トリプトファンとチロシン(集中力と活力)
夜:グリシンやGABA(睡眠導入と安定)
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。